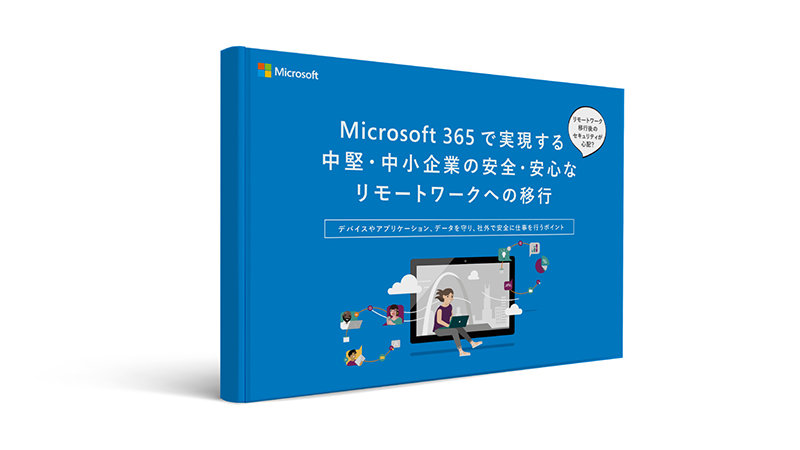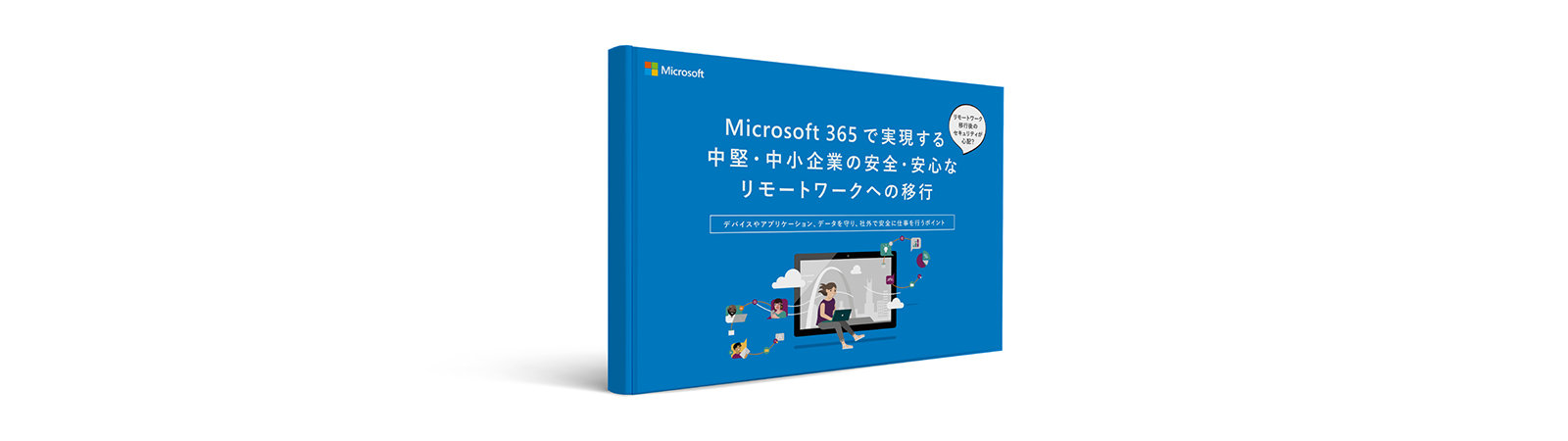1. DX とは?
まずは、「DX」という言葉の意味を正しく理解したいと思います。
1-1. 「DX」という言葉自体の意味
DX は、「デジタル トランスフォーメーション = Digital Transformation」の略語で、2004 年にスウェーデンのウメオ大学教授、エリック・ストルターマン氏が提唱した概念。「進化し続けるテクノロジーが人々の生活を豊かにしていく」ことを意味しています。英語表記は「Digital Transformation」であるにもかかわらず、「DT」ではなく「DX」と表現することに違和感を覚える人もいるかと思いますが、英語圏では「Trans」を「X」と略すことが一般的であるため、このように表現されているようです。
1-2. 日本における DX の定義
日本における DX の定義を正しく理解するには、経済産業省が発信する「デジタル トランスフォーメーションを推進するためのガイドライン (DX 推進ガイドライン)」の表現が参考になります。そこには「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネス モデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」という記述がありますが、要するに、企業がデジタル技術を活用し、ビジネス モデルや企業そのものを変革していくことを意味しています。
英語の「デジタル トランスフォーメーション = Digital Transformation」を直訳すると「デジタル変換」になりますが、経済産業省のガイドラインにあるように、単なる“変換”ではなく“変革”という意味合いを持っていると理解すべきでしょう。